【初心者向け】ペット保険の基礎知識から選び方まで徹底解説まとめ
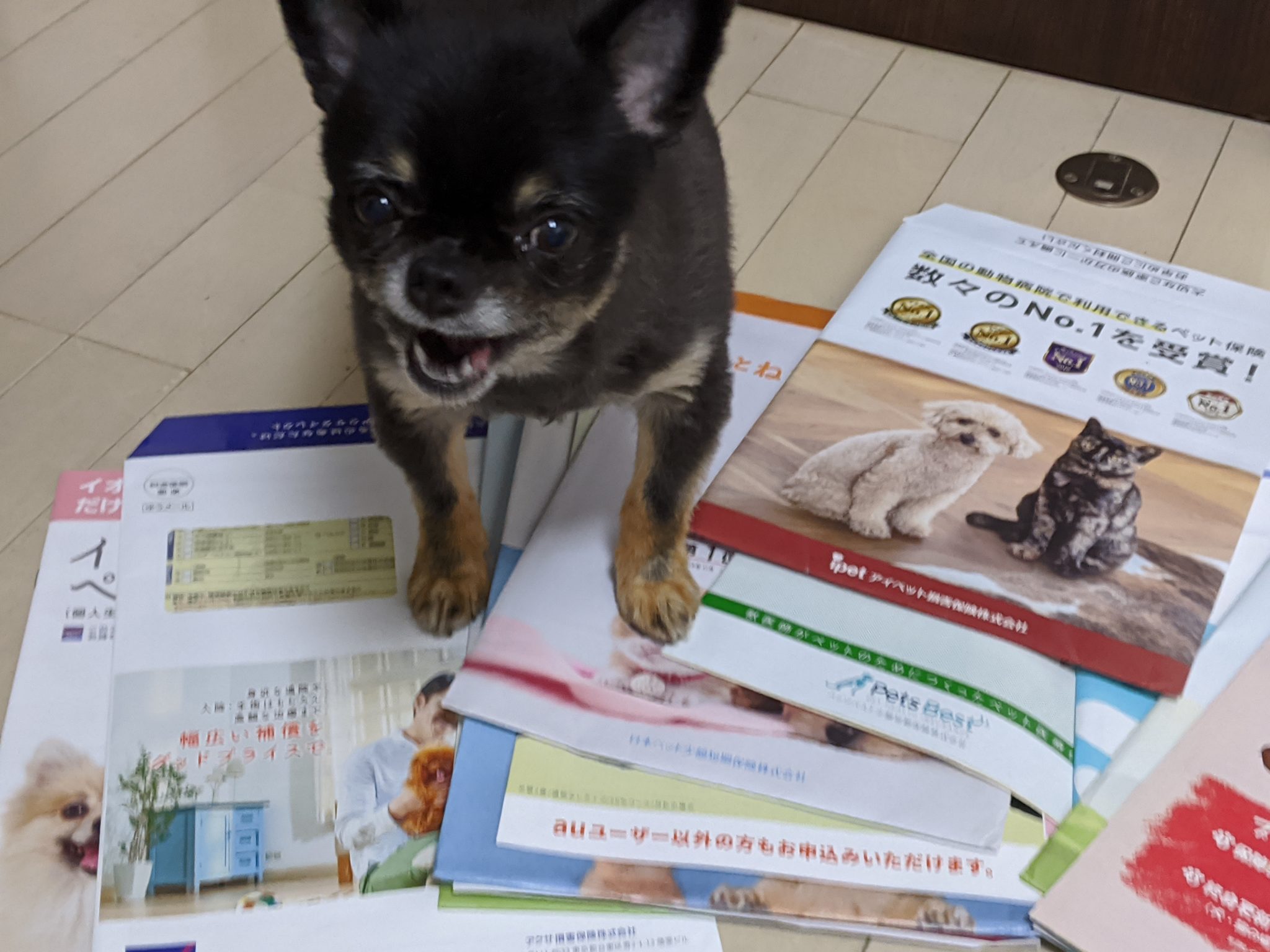
こんにちは!チワワ君の飼い主です。
ここでは、ペット保険についての基礎的なところから実際にペット保険選びで大事なところまで、全てを網羅したページになっています。
このページをみていただくと、ペット保険の知識が0からでもしっかりとペット保険についてA to Zで理解できるようになっているので、ぜひ何度も読み返せるようにブックマークなどでしておいてくださいね。
ペット保険は必要か?
ではまずはそもそもペット保険は必要なのか?という論争について。大体貯蓄で十分か、ペット保険に加入するべきかという対立構造になるのですが、私の見解とペット保険に加入するかどうかの判断基準は以下のページをご覧ください。ついているものがあります。
全ペット保険共通で対象外となる病気やケガ
ペット保険会社やプラ添付よって異なる病気また、
ペット保険会社やプランによって異なる病気やケガについて※準備中
ペット保険の基礎知識
では次にペット保険に関する基礎知識について紹介していきます。一般的な保険に関する知識やペット保険特有の知識についてここでしっかり確認しておきましょう。
ペット保険会社の種類
まず、ペット保険と一言で言っても実は3種類に分かれます。それが損害保険、少額短期保険、ペット共済です。(※ペット保険については厳密には保険ではありませんが、便宜的にこちらに加えています。)
ペット保険で加入可能な動物
ペット保険で取り扱いができる動物については、実はペット保険によって異なります。基本的には犬と猫のみの取り扱いしかないペット保険が大半ですが、うさぎやモルモットなどの小動物や鳥類、爬虫類も加入できるペット保険もあるため、加入する動物によって検討するべきペット保険が異なることに注意です。
※ペット保険で加入可能な動物について(※準備中)
ペット保険の加入条件
では次にペット保険に加入する際に確認しておく条件について紹介していきます。
加入、更新上限年齢
まずは年齢について。ペット保険は各ペット保険会社が定めた年齢を超えるとペット保険の加入自体ができません。以下にペット保険会社ごとの加入できる年齢制限についてまとめました。(※一部年齢上限のないペット保険もあります。)
また、更新できる年齢制限ですが、現在はすべてのペット保険が上限なし(何歳まででも更新可能)となっています。
告知義務について(既往症・過去の病歴)
ペット保険加入時には必ず現在の進行中の病気やケガ、そして過去に患ったことのある病気やケガ(既往症)についての告知をする義務があります。
ここで1つ注意なのが、現在進行中のけがや病気については補償対象外となります。
また、現在治療中の病気やケガ以外にも、過去に発症して一度完治している病気やケガ(既往症)についても告知する義務があります。
一度完治してれば加入時に同じ病名で発症した場合、基本的に補償対象とはなりますが、再発の高い病気などによっては、一度完治していても、免責疾病として補償対象外とされたり、保険の加入自体を断られる場合があるため注意が必要です。
ペット保険の補償内容
では、次にペット保険の補償内容についてみていきましょう。ペット保険特有の補償内容も多いため、まずは基本的なところから押さえていきましょう。
年間最大補償金額
まずは、まるっと年間で請求できる保険金の最大補償金額が各ペット保険会社ごとに違います。この金額が大きければ大きいほど多くの保険金を受け取ることができるともいえるのですが、実はそうとも言い切れません。
実際には最大補償金額とは別に通院、入院、手術でそれぞれ年間で請求できる回数や1回(1日)あたりの請求金額に制限がついているタイプの保険と、前述の枠関係なしで請求できる保険とがあります。
前者の場合は最大補償金額の中にさらに制限の枠があるため、最大補償金額を使い切るのは難しくなります。ペット保険会社が打ち出す最大補償金額が高いからといって、それが補償の厚さに直結しないところに注意が必要です。
年間の補償回数、1回の補償金額の制限があるペット保険とないペット保険一覧
補償条件(通院、入院、手術のフルカバーか手術のみなど部分プランか)
次に補償条件について。ペット保険の補償対象となるプランについては、通院、入院、手術とすべてをカバーしているフルカバープランと、通院のみ、または入院や手術のみなど部分的な補償に限定されたプランがあります。フルカバーだからいい、部分補償だから悪いということはなく、部分補償の場合はその分保険料が抑えられるというメリットもあります。それぞれの特性を理解したうえで、ペット保険に加入する目的に合ったプランを検討することが大事です。
補償額の割合(50%、70%、100%)
次にペット保険の補償割合について。最も一般的なのは70%プラン。人間の健康保険と同じく3割の自己負担となるプランです。そのほかに50%プラン、中には治療費の100%を補償してくれるプランもあるので、それぞれしっかり内容を確認したうえで加入を検討しましょう。
待期期間について
ペット保険加入後に注意しなければいけないのが、待期期間。
ペット保険の申し込みを行い、契約が開始されたとしても実はまだ補償期間はスタートしないペット保険がほとんどです。それは、契約スタート後に保険金請求の補償対象外の期間が一定存在するためです。それが待期期間。
待期期間は大体30日~60日が設定されているペット保険がほとんどで、まれに待期期間が無い=契約スタート後にすぐ補償期間がスタートするペット保険もありますが、注意が必要です。
保険金の受取方法
次に保険金の受け取り方法について。保険金の受け取り方は保険会社によって2パターンに分かれます。
窓口清算
窓口清算は特にこちら側がすることはありません。人間の医療保険制度と同じように、対象となる治療費に対して、加入しているペット保険のプランの補償割合分を差し引いた費用を支払うだけで完結します。
たとえば、70%補償のプランに加入していて1万円の治療費だとすると、3000円を窓口で支払うだけで完結します。注意点としては、指定のペット保険毎に窓口清算できる動物病院が決まっていて、その動物病院以外を受信した場合は窓口清算ができないところです。
といっても、次に紹介する後日清算を行えば保険金の請求はしっかりできるので、最寄りの動物病院が加入しているペット保険の窓口清算病院として提携していなくてもご安心くださいね。
また、窓口清算のできるペット保険は現在以下の3つのペット保険会社に限られます。
後日清算
後日清算は動物病院では治療費は全額支払う必要があり、後日保険金をペット保険会社へ請求→指定口座へ振り込み、という流れとなる清算方法。
窓口清算に対応しているペット保険が3社に対して、それ以外のペット保険はすべてこの後日清算に該当します。(※実際、窓口清算のペット保険でも提携外の動物病院では後日清算の方式となるため、実質すべてのペット保険はこの後日清算に対応しているといえます。)
以前はマイページや電話で請求用紙を取り寄せて、そこに必要事項を記入し診断書を同封して返送する、という少々面倒な作業でしたが、今は専用アプリからオンラインで請求が完結したりと非常に便利になっているので、個人的には後日清算でも十分問題ないと感じます。
免責金額とは?
次に免責金額の設定について。免責金額とは平たく言うと、自己負担額のこと。
たとえば、免責金額1日3000円の70%補償のペット保険に加入していたとすると、1万円の治療費の請求をする場合、1万円-3000円=7000円、7000円×0.7=4900円の受け取り保険金となる、という計算になります。
免責金額の設定があると、その分受け取り保険金は減少しますが、その分保険料が低く抑えられるというメリットもあるため、一概にデメリットとも言えません。
免責金額設定のあるペット保険
複数のペット保険のかけもちについて
以外に思われる方もいるかもしれませんが、ペット保険の加入は1つだけではなく、2つや3つといった複数の保険に同時加入が可能となっています。
掛け持ちをする一番の理由は、1つでは心もとない補償を複数のペット保険に加入することで補完することです。ただ、保険料もその分多く支払うことになります。
また、当然と言えば当然ですがすべてのペット保険会社から受け取れる保険金の合計は治療費の全額を超えることはありません。たとえば、1万円の治療費に対し70%プランのペット保険2社にそれぞれ保険金の請求をしたとします。
通常の計算をすると、各7000円ずつ保険金がもらえて14000円を受け取れますが、先ほど説明した制約から受け取れる保険金は治療費の全額1万円までとなります。それぞれのペット保険会社へ7000円の請求をした場合でも、ペット保険会社間で調整が行われることになっています。
ペット保険加入時の付帯サービスや特約
ペット保険の加入時に便利なサービスや補償を追加できるものがあったりします。別途費用が発生するものが特約、別費用は発生せず該当のペット保険に加入することで自動的に利用できる付帯サービスとがあります。
付帯サービス
獣医師見守りサービス
獣医師見守りサービス付帯のペット保険
腸内フローラ検査
腸内フローラ検査付帯のペット保険
特約
通常の契約とは別につけることができる(もしくははじめからついている)オプションを特約といいます。付帯サービスと似た部分はありますが、特約は加入が任意であったり、通常の保険料にプラスして費用が発生するところが異なる点です。
ここでは、ペット保険でつけることのできる特約について紹介します。
個人賠償責任特約
これは、ペットが外出先でものを壊したり、他人を傷つけてしまった場合などの補償をカバーしてくれる特約。ほとんどのペット保険でつけることができ、毎月の保険料は数百円ほどが一般的。
注意する点としては、個人賠償責任特約はペット保険以外でも加入できて、特に自動車保険などに着けている方は多いと思います。すでに何かしらの保険で特約をつけているのであれば、二重に加入となるため、この特約をつける必要はありません。
まだ加入していない方で、特にペットと外出する頻度が多い方などは、加入するペット保険で入っておくのはおすすめです。
特定のペット保険のみで付帯できる他の特約
また、特定のペット保険のみで付帯できるユニークな特約もあります。それが、車いす特約や火葬費用(ペットセレモニー)特約などがあります。
車いす特約はペットが事故によって歩行困難になった場合の車いす費用を補助してくれる特約で、下層費用特約は文字通りペットが亡くなった際の火葬費用を補助してくれる特約。
また、飼い主がペットを飼育できなくなった際、ペット保護団体への譲り渡し費用を補償してくれるといったユニークな特約もあります。
いずれも日常的に使える特約ではないので、これがペット保険選びの決め手にはならないとは思いますが、加入したペット保険で利用できる特約が付帯されていないかなどは、事前に確認しておきましょう。
日常の保険料に直結する特約としては、免責金額は必ず発生する自己負担金のことですが、これをあえてつけることで保険料を通常よりも抑えて補償を受けることができる特約もあります。
車いす特約が付帯するペット保険
火葬費用特約が付帯するペット保険
飼育費用補償が付帯するペット保険
免責金額適用特約のあるペット保険
ペット保険の保険料の考え方
ペット保険の保険料について説明します。ペット保険はすべてが掛け捨てになっており、各ペット保険はペットの種類や犬種によって保険料が決まっています。
ペット保険の選び方として、ペット保険加入時の保険料はしっかり確認する方がほとんどですが、加入後の保険料についてよく調べてから加入する方は案外少ないです。
というのも、先ほどお話しした通りペット保険は基本的に年齢が上がるにつれて上昇していきます。ただ、その保険料の上がり方が各社で違い、加入直後の保険料は同じくらいだったのに、数年後には2倍の差がつくペット保険もあったりするのです。
保険料の割引制度
ペット保険によっては保険料の割引制度のあるものもあります。2頭以上加入するとペット保険が割引になる多頭割引や一定期間保険金の請求が無いと適用される健康割引などがあります。
ペット保険会社について
ペット保険選びの最後の項目はペット保険会社そのものについて。保険料や補償内容など直接的な部分ではないですが、ペット保険会社の経営状態や経営基盤なども関係してきます。
というのも、ペット保険という業界自体がペット保険の参入と撤退、契約の改訂などがたびたび行われるため、現状の条件だけをみていても、今後変わってしまったり、ペット保険会社自体が無くなってしまうリスクはどうしてもつきまとうのです。
契約者にとって条件がいい=資金調達や利益のあがる構造を作る難易度が上がる、ということなので、一瞬良い条件で加入者を集めたとしても、経営体力がないと維持することができず結局撤退する・・というのはありがちです。
確かに現状の条件を比較するのは基本ですが、あまりにも条件が良すぎる場合などは、ペット保険会社自体の母体(出資元)や参入して間もない会社なのか、それとも業界内で長年続いている老舗なのか、という会社の信用という部分もペット保険選びでは大事だと思っています。
ソルベンシーマージン比率
ソルベンシーマージン比率とは、保険会社が様々なリスクが起こった際に、支払うことのできる保険金の支払い余力がどれだけあるか、というのを表したパーセンテージのこと。
一般的な基準値として200%以上のソルベンシーマージン比率があると健全な経営状態であると言えます。
ペット保険についてのQ&A
では最後に、ペット保険についてよくある質問をまとめます。
ペット保険の再加入はありですか?
全く問題ありません。むしろ、加入したらずっと同じペット保険を継続し続けるというよりも、ペットの年齢やライフスタイルに合わせて定期的に見直しをするのがおすすめです。
一点注意点は、再加入する際の既往症や健康状態の告知次第では、不担保条件(補償対象外)の疾病などが付く可能性があるところです。現在のペットの健康状態によっては、条件だけをみて乗り換えると、結局不担保条件によって乗り換えない方がよかった、というなる可能性もあります。
保険金請求の後日清算は具体的にどんな流れですか?
保険金の後日清算の具体的な流れは以下です。
- 動物病院で診察、治療、薬をもらう
- 治療費の全額を動物病院へ支払う
- 各社の保険金請求のフォーマット(書面、アプリなど)で保険金の請求(このとき動物病院でもらった治療費明細、診断書などを添付)で保険金請求
- 受理され次第、登録している指定の銀行口座へ振り込みがある
短期間に何回も治療費が発生する場合は、逐一請求せずにまとめて請求すると手間が省けます。
ペット保険解約する際の注意点はありますか?
解約をする際の注意点としては、年齢によってはもうペット保険の加入ができなくなること、また再加入する際の健康状態によって不担保条件(補償対象外)の疾病などの条件がついてしまう場合があることです。
逆に言うと上記以外は解約のデメリットはほぼありません。保険料も継続加入しているからといって割引になったりもしないですし、掛け捨てなのでいつ解約しても損をすることはありません。(※保険金を年額払いしていた場合、解約時期によっては満期までの保険料の払い戻しをしれくれます。)




